











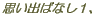



 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||||
 |
 |
|||||||||
 |
 |
 |
||||||||
 |
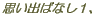 |
 |
 |
 |
||||||
| 三四郎さまが、時間を掛けて丁寧に書き下ろしてくださった新しい見解から書かれた近衛十四郎ストーリーです! 三四郎さまのご許可のない無断転写は、ご遠慮下さいませ。 |
|
近衛十四郎の実演時代 日本一と謳われた立回りが生まれた経緯を探る 〜松竹、東映時代の序章〜 未 完 |
|
| 日本映画は誕生して百年以上に及ぶ長い歴史の中、その活劇の原点であるチャンバラで一世を風靡した時代劇俳優を数多く輩出した。 映画スターの第一号でもある「目玉の松ちゃん」こと尾上松之助を嚆矢に、七剣聖といわれる阪東妻三郎、片岡千恵蔵、市川右太衛門、嵐寛寿郎、長谷川一夫、大河内伝次郎、月形龍之介。 さらに時代を下って勝新太郎、市川雷蔵、中村錦之助(萬屋錦之介)、大川橋蔵など、ひとりひとり名前を挙げていってはキリがないが、彼らは“剣戟スター”と呼び習わされ、その豪快かつ華麗だった立回りは、今現在でも多くのチャンバラ映画ファンの語り種となっている。 そして、これらの剣戟スターの中で、戦後の一時期「立回り日本一」を謳われていたのが近衛十四郎である。 今日、娯楽チャンバラ映画を語らせて右に出る者が無い評論家の永田哲朗氏は、殺陣の流れを通した時代劇史である『殺陣―チャンバラ映画史―』(現代教養文庫刊、以下『殺陣』と略す)の中に「近衛十四郎の殺陣」という一章を特別に設けて、自身の近衛に対する熱い思いを綴っており、その冒頭部分でこう述べている。 昭和三十年代から四十二、三年ころまで、東映、大映、松竹など、どの社の殺陣師に聞いても、「一番アブラの乗っているのは近衛だろう」という答えが返ってきたくらいで、私は「剣豪スター番付」を作ると、必ず近衛を横綱に置いた。 立回りについてはもっともうるさい評論家の大井広介氏も「近衛十四郎、宍戸錠、佐藤允のえいがは必ず見ている」といっていたところを見ると、やはり一番高く買っていたのではないか。 近衛は阪妻の豪快さと、大河内のニヒルさ、寛寿郎の鋭さというキャラクターをあわせ持ち、立回りはダイナミックで迫真力があり、スピードといい、型のキマリ具合といい抜群で、正に一時代を画するものだったと永田氏は絶賛する。 だが、映画では近衛の実力は生かされず二線級にとどまり、知る人ぞ知るという域を出ずじまいで、昭和四十年にはじまったテレビの『素浪人月影兵庫』によってようやく一般的な人気を得、多くの人が見ることによって立回りの真価も認められたものの、テレビに出たときは四十九歳ですでに全盛期を過ぎていた。 それに、たとえば『三匹の侍』の五社英雄ディレクターとでも組んでいたら、何も月影兵庫のようなコミカルなものでなくとも大いに茶の間のファンをわかせたはずで、その怒りともどかしさを映画界にぶつけたかったのだと、『殺陣』の中で特に近衛について頁を費やすに至った思いを吐露している。 近衛が剣戟スターとしての名声を打ち立てたのは古く、昭和十年代のはじめ、B級の活劇を主に製作していた大都映画の時代劇においてである。 当時はまだ活気横溢した二十代前半の青年俳優で、スターの序列も阿部九州男、海江田譲二、松山宗三郎に次ぐクラスだったが、現今の我々が想像する以上の人気があり、次代を担うホープとして将来を嘱望された。 ところが、日本が太平洋戦争へ突入して間もない昭和十七年一月、新興キネマ、大都映画、日活製作部門の合併によって大日本映画(大映)が発足するのと時を同じくするように、近衛は二十八歳の若さで「近衛十四郎一座」を旗揚げして映画界に見切りを付け、実演に走る。 そして、すでに不惑も近い三十九歳を迎えようとする昭和二十八年に映画界へ戻り、正式に映画俳優としての再スタートを切るのだが、約十年間映画界を遠ざかっていたことが災いし、ポスターに名も載らない端役に近いところからの出直しを余儀なくされた。 しかし近衛は、端役に近いところからの出直しという大きなハンディを乗り越え、主演スターの座へカムバックする。 その奇跡の呼び水となったのが、彼の立回りだったのである。 それだけに、近衛本人も立回りには並々ならぬ自信を持っており、“剣のスター”を自称し 「俺の立回りは日本一だ!日本一ということは世界一だ!」 と、こう言ってはばからなかったという。 もっとも、戦前の昭和十六年八月に公開された大都映画のオールスター作品『柘榴一角』(監督 白井戦太郎)を観る限り、近衛の立回りはいまの若い俳優ほどひどくはないものの、戦後のそれと比べるとかなり見劣りがする。 かれは『素浪人月影兵庫』の続編である『素浪人花山大吉』の放送終了後、悪化の一途を辿っていた糖尿病の療養のため約二年間にわたり映画とテレビドラマの仕事をセーブし、それまであまり縁のなかったテレビ各局のトーク番組へ妻のやゑをともない出演したが、そのひとつに、フジテレビの『笑ってる場合ですよ!』がある。 これは、昼の十二時に新宿のスタジオアルタから放送されていた公開バラエティショーで、番組がはじまってしばらく、やゑとともに客席でコントを楽しんでいた近衛は、ゲストコーナーになって万来の拍手を浴びてステージに上がり、総合司会をつとめる漫談家のコロンビア・トップと対談した。 ひととおりの紹介が終わったあとの、 「あたしゃ座頭市も(昭和四十二年十二月に公開された、三隅研次監督、勝新太郎主演による大映映画『座頭市血煙り街道』のこと)、あなたの立回りが見たくてわざわざ映画館へ出かけたほどでね」 というコロンビア・トップの言葉がいまでも印象深く残っているが、これに対し 「僕はねえ、もともとチャンバラが好きなんですな。それで、若いころ一座を組んで地方巡業をずいぶんしたんですが、そのとき、座員と血だらけ痣だらけになるほど、チャンバラのイロハをみっちりやったんです。僕の立回りが少しは褒められるのは、それが身になったんでしょうな」 と、このように近衛は応えていたと記憶しており、永田氏の『殺陣』には以下の記述がある。 少し長いが、ふたたび引用する。 松竹の殺陣師川原利一氏は、「うますぎる。どういう手でもこなしてくれる。大きな体でよくきれいに動くと感心している」と、近衛の立回りを評していた。 川原氏によると、ふつう侍の刀は、腕を真っ直ぐに下げて、その先端が地面につかない長さのものを選んで使っている。 大体七十五〜八十センチになるが、八十五センチもの長い刀を注文して好んで使っているのが近衛で、ふつうの人では使いきれないような長さだが、近衛はその方が使いやすいのだという。 これは舞台では長い刀のほうが映えるからで、凄みも出る。 また彼の剣さばきは上へ斬り上げるものが多いのも舞台映えするためだ。 川原氏はまた、 「近衛さんの剣は非常にセッカチというのか、カラミがかかってこないのに自分の方からかかっていく。これも聞いてみると舞台生活の影響だという。カラミが次から次と間合よくかかってくれればいいのだが、地方巡業のレベルではなかなかそうもいかない。現在の松竹のカラミがそれほどヒドいものではないにしても、近衛さんにはまだ不満があるらしく、そういう弱点をカバーするため、自然と主役らしくない殺陣になるのだ」 ともいっていた。 この近衛本人と川原利一の話から、実演時代に繰り返された座員との正に血の滲むような激しい殺陣の練習が、「日本一」と謳われる立回りを生んだのだとみてまず間違いない。 あらためていうまでもなく、近衛の劇団は剣劇一座であり、立回りが最大の売り物だったのであるから、これが座員と激しい殺陣の練習を繰り返した理由だったといっても差し支えないようにも思われるが、私はもう少し踏み込んだ見方をしている。 この当時、戦争の影響による映画製作本数の削減で、活躍の場を失った中堅スターがいっせいに一座を組んで、“映画スターの実演”を売り物に巡業したのだが、最後まで残ったのが近衛だった。 戦後、この人たちがぞくぞく映画界へ復帰するのを尻目に、 「そんなら俺ひとりだけでも頑張ってやろうと思った」 とは近衛の話だが(『殺陣』)、これまでのところ、なぜ近衛が最後まで実演に残ったのかについてはわかっていない。 しかし、断片的に残されている近衛一座の足跡を繋ぎ合わせると、近衛はこれまでに言及されたことが無い、自身のある意外ともいえる決意によって最後まで実演に残った可能性が高い。 そして、この決意が座員との激しい殺陣の練習を繰り返させた、いや、繰り返さざるを得なかったのだと、こう私は見ている。 したがって、松竹、東映時代のプロフィールを記す前に、私はまず順序として、この、これまで言及されたことの無い、意外ともいえる近衛の決意とはいったいどのようなものであったのかを明らかにすることとした。 これが、松竹、東映時代の序章として『近衛十四郎の実演時代』という一章を設け、さらには「日本一と謳われた立回りが生まれた経緯を探る」というサブタイトルを付けた所以である。 ただし、この近衛の意外な決意というのを明らかにするためには、戦中戦後の剣劇そのものの動向を詳しく見なければならない。 あわせて、近衛が一座を旗揚げするに至った経緯についても改めて検証する必要があり、便宜的に彼が映画界へデビューする時点にまで遡って筆を起こすことにした。 そのため、この『近衛十四郎の実演時代』は、かなりの長文になることをあらかじめお断りしておく。 |
|
| 近衛十四郎は昭和七年十八歳の時に、奈良県あやめ池にあった市川右太衛門プロダクション、通称“右太プロ”の研究生からスタートした。 もちろん回ってくるのはその他大勢のエキストラといってもいい端役ばかりで、現時点においてはただ一本だけ、役柄等はまったく不明ながら、右太衛門が出ない映画を専門に製作する市川右太衛門プロダクション第二部の、尾上栄五郎主演映画『旅役者二刀流』(昭和七年四月公開。監督 古野英治)に出演しているらしいことが、永田哲朗編『日本映画人 改名・別称事典』(国書刊行会刊)に書かれている。 余談ながら、黒澤明が監督としてはじめてメガホンを取った東宝映画『姿三四郎』(昭和十八年三月公開)に主演し、戦後の昭和三十二年に公開された近衛主演の松竹映画『浪人街』(監督 マキノ雅弘)へ母衣権兵衛役で出演した藤田進。 彼は昭和三年に福岡の南筑中学(現久留米市立南筑高等学校)を卒業後、東京へ出て大学を受験するも、失敗。 その帰途に京都へ立ち寄り、右太プロにいた郷里の先輩(昭和八年に監督として大都映画へ入社する大伴麟(龍)三ではないかと思われる)を訪ねたさい役者になるよう勧められ、昭和四年から約一年間右太プロでエキストラをしていた。 さらに蛇足として付け加えると、右太プロは、右太衛門が京都双ヶ丘にあった松竹第二撮影所の専属となったため、昭和十一年に解散。 その撮影所跡地に、右太衛門の兄である山口天龍が全勝キネマを設立し、昭和十七年の企業統制によって松竹に吸収されるまで、低コストによる映画を製作した。 さて。― 昭和七年当時、右太プロに近衛八郎の名があり、これが十四郎だと思われていたのだが、まったくの別人。 このころは故郷の新潟県長岡から採った長岡秀樹を称しており、近衛十四郎を名乗ったのは右太プロから日活京都へ引き抜かれた後、弁慶の新太役で出演した、昭和八年三月公開の坂東勝太郎主演『ちりめん供養』(監督 池田富保)からで、命名者は右太プロ時代に可愛がられた白井戦太郎監督だと云われる。 白井戦太郎は、右太プロで社会派の監督として有名だった古海卓二に師事し、昭和二年十一月に公開された右太衛門主演の『怒苦呂』で監督に昇進した後、嵐寛寿郎プロダクションを経て、昭和九年、京阪線牧野の旭ヶ丘に“労働団結による合理的経営”を旗印とした亜細亜映画プロダクションを設立。 右太プロから日活京都へ引き抜かれ、「いずれは主演作を撮らせるから」とはいわれるものの、映画界一の名ショートだった野球の腕ばかりが買われ、役者としては泣かず飛ばずの状態が続いていた近衛も、この亜細亜映画プロダクションに参加。 昭和九年四月に公開された亜細亜映画プロダクションの第一回製作作品『叫ぶ荒神山』(監督 白井戦太郎)の吉良の仁吉で、はじめて主役を張った。 もっとも、企画段階でこの『叫ぶ荒神山』の主役に立てられたのは近衛ではなく、結城重三郎という俳優だった。 ここでキネマ旬報社の『日本映画俳優全集 男優編』を参考に結城重三郎についていささか筆を費やせば、彼は助監督として映画界入りを希望し、大正十四年に伝を得て帝キネのスター津村玉枝を尋ね、斡旋を頼んだ。 ところが図らずも、これまた帝キネのスターだった尾上紋十郎に無理やり弟子入りさせられ、尾上紋禄の芸名をもらい、俳優として帝キネ小阪撮影所へ入社。 その後、帝キネの別派であるアシヤ映画に移って結城三重吉と改名し、さらにマキノ、山口俊雄プロと渡り歩いた。 山口俊雄プロが解散すると、有馬是馬らと旅回りの一座に入るなどしたが、昭和五年にふたたび帝キネへ戻って芸名を結城三重吉から結城重三郎に改め、寿々喜多呂九平監督の『鉄血三羽烏』(昭和六年四月公開)に主演。 昭和六年十月に帝キネが新興キネマになってからも、『親分商売』(昭和六年十一月公開。監督 並木鏡太郎)『武州の双龍』(昭和六年十一月公開。監督 松田定次)などに主演した。 翌る昭和七年、宝塚映画をやめた剣戟スターの羅門光三郎が原駒子と設立した富国映画社へ入り、橋本松男監督の『渡世くづれ』に主演するも、富国映画社は昭和八年一月に日本映画によって配給された『浪人の行く道』(監督 山下秀一)の製作を最後に活動を中止。 やむなく「結城重三郎剣劇団」を旗揚げし旅に出るのだが、山陽路を旅していると旧知の中川紫郎監督の訪問を受け、志波西果が月形龍之介の参加を得て設立した朝日映画聯命の第二作『海援隊快挙』(昭和八年十月公開。監督 志波西果)に、月形の坂本龍馬に対して中岡慎太郎役で出演してくれれば必ず主演作を撮るからと誘われて一座を解散し、出演に応じた。 しかし朝日映画聯命は、『海援隊快挙』を製作したのを最後に倒産。 結城は残された役者とともに東京の場末の劇場を回って、アトラクションなどに出演して辛うじて職にありつくいっぽう、帝キネ時代に知り合った女優の久野あかねと結婚、一女をもうけた。 さらに昭和八年五月、新宿のムーランルージュにいた知人を訪ねたさい、上演中だった伊馬鵜平の『溝呂木一家十六人』を観て感動。 ふたたび出た旅先から舞台の脚本を書いて送り、そのうちのひとつ『実力忠臣蔵』が認められたことでムーランルージュ文芸部へ入り、それと同時に役者をやめる決意をした。 この間、白井戦太郎が亜細亜映画プロダクションを設立。 その第一回製作映画『叫ぶ荒神山』の主役・吉良の仁吉に、前々から白井の映画へ出演することを約束させられていた結城が立てられたのである。 しかし結城は、ムーランルージュの文芸部に入っており、役者もやめるつもりでいる。 そのため、主役の吉良の仁吉を近衛に譲って自身は脇の神戸の長吉へ回り、白井との約束だけは果たすこととしたのである。 亜細亜映画プロダクションの『叫ぶ荒神山』ではじめて主役を張った近衛は、続く五月に公開された『曲斬り街道旅』(監督 白井戦太郎)にも主演する。 ところが、亜細亜映画プロダクションはメジャー会社に対抗できず、心機一転、六月に社名を第一映画社に変更。 みたび近衛を主役に据え牧野で撮った『天保からくり秘帖』(監督 白井戦太郎)を九月に公開するも、今度は室戸台風に直撃され撮影所が倒壊。 これによって第一映画社は解散せざるを得なくなり、翌る昭和十年に、近衛は白井とともに大都映画へ入社するのである。 これまでのところ、近衛が白井とともに大都映画に入社することになった経緯については詳らかにされていない。 だが、右太プロで白井とともに古海卓二に師事していた大伴麟(龍)三が、昭和八年から大都映画の監督をつとめている。 したがってこの大伴が、近衛と白井の大都映画入社に一役買ったということは、じゅうぶんに考えられよう。 ちなみに『叫ぶ荒神山』への出演を最後に、ムーランルージュで本格的に脚本・演出家としての活動をはじめていた結城重三郎は、なんと近衛よりも先に大都映画に迎え入れられていた。 昭和九年の暮れ、ムーランルージュの稽古場に大都映画の社長河合徳三郎が監督の石山稔をともなって訪れ、男装の女剣士役などで人気があった三城輝子(河合の次女)の相手役として大都映画に入社してくれるよう懇請。 結城は驚くとともに「自分はもう役者はやめたから」と申し入れを固辞したのだが、 「わしが頼みに来たのに断るとはエラい男だ」 とかえって河合に惚れ込まれ、その挙句に膝詰め談判となり、やむなく大都映画へ入社する羽目になったのである。 そして河合から松山宗三郎の芸名をもらい、ふたたび剣戟スターとして活躍する傍ら、小崎政房の本名で脚本家・監督としても良心的な現代劇を数多く世に送り出し、とりわけ昭和十三年十一月に公開された水島道太郎主演の『級長』は、大都映画現代劇の最高傑作として評価が高い。 |
|
| 近衛が亜細亜映画プロダクションから主演スターとして売り出されたころ、日本国内の映画市場は日活、松竹、新興キネマ、大都映画が支配するという構造が一応出来上がっていた(昭和十二年になると、PCL、JOスタジオ、東京宝塚劇場から成る東宝が、新興勢力として加わる)。 そして昭和十一年には映画館入場者数が二億人を超え、その大多数が二十歳代までの青少年で、うち四人にひとりは十四歳未満の「小人」、つまり子供だったという記録が残されている。 なかでも、当時の日本映画の主流だった時代劇のチャンバラを目当てに来る男性が圧倒的に多く、したがってスターの格も、現代劇より時代劇の方が上だった。 ここでやや時期は前後するが、主要邦画各社が抱えていた主な時代劇スターの顔ぶれを見ておく。 まず最大手である日活には、昭和十一年に大河内伝次郎と黒川弥太郎がJOの引き抜きにあった後、翌る十二年にいずれもプロダクションを解散した阪東妻三郎、片岡千恵蔵、嵐寛寿郎の三大スターが結集。 日活とならぶ大会社の松竹では、美男で売った林長二郎(長谷川一夫)が看板スターとして時代劇を支えていたが、彼もJOに引き抜かれ、その後を高田浩吉、坂東好太郎、川浪良太郎が埋めた。 しかし林の抜けた穴は大きく、松竹時代劇はたちまち不振に陥る。 松竹時代劇が不振に陥った間隙を衝いたのが、その松竹の傘下におさめられていた帝キネを昭和六年に改組した新興キネマで、浅香新八郎、大谷日出夫らを擁し、前身の帝キネと同様、下級観客層向けの時代劇を製作した。 もっとも当初は業績は不振で、昭和十一年に、第一映画を解散したばかりの永田雅一を専務取締役兼京都撮影所長に据えて挽回を図り、入江たか子の怪猫ものなどの新企画を打ち出してゆき、翌る十二年には、双ヶ丘の松竹第二撮影所の専属となっていた市川右太衛門が松竹の意向によって入社し、『青空浪士』(監督 押本七之助)で大友柳太郎(柳太朗を称するのは戦後)もデビュー。 さらに昭和十三年には、マイナーの大統領といわれた羅門光三郎が今井映画から入社するなどして興行価値豊かな娯楽時代劇が数多く作られるようになり、業績もようやく上向き始め、主に下級階層の婦人たちの人気を得た。 そして大都映画は、政財界とも繋がりを持つ土建業界の大ボスで任侠の徒でもあった、「河合組」の総帥河合徳三郎によって設立された河合映画社を昭和八年に発展的改組した映画会社で、東京の巣鴨に撮影所を構え、百五十前後の系列館があった。 理屈抜きの娯楽作品を一貫して低コストで制作したため入場料も二十銭均一と安く(地方には十銭席もあった)、評論家や同業者からは「粗製乱造、三流」などと酷評されたが、つましい生活をしている大衆からは絶大な支持を得、当時のファンの熱狂的な回想があり、研究書もいくつか出版されており、戦後、東映時代劇で粗暴なワルを専門に演ずる阿部九州男と、日活時代に澤田清と人気を二分したこともある海江田譲二が二大スターとして君臨していた。 昭和十年に白井戦太郎とともに大都映画へ入社した近衛は、四月に公開された阿部が主演する『国柱日蓮大聖人』(監督 中島宝三)の日朗役でファンに初お目見えしたあと、『奇人豪傑三人旅』(監督 石山稔)で、松山宗三郎と改名した結城重三郎とふたたび共演。 続く五月に封切られた『銀平くづれ格子』(監督 白井戦太郎)から主演スターとして一本立ちし、殊に昭和十年十一月から翌る十一年一月にかけて公開された『疾風蜥蜴鞘』三部作(監督 白井戦太郎)は、昼は飴屋で夜は怪盗と神出鬼没、サイレント乱闘活劇の醍醐味を満喫させたというが、近衛は当時としては大柄な百七十センチという堂々たる体躯を生かした青年剣士役で、忽ち少年ファンのアイドルとなった。 先に触れたように、このころ、日本映画の主流は時代劇だった。 そのいっぽう評論家の多くは、時代劇はチャンバラが見せ場の子供向け映画で質の低いものと見ていた。 しかし、これも前に述べたように、映画館来客数の四分の一は子供だったのだから映画産業にとって子供は決して無視することの出来ない存在だったのであり、小説『麻雀放浪記』で有名な作家の故阿佐田哲也が、色川武大の本名で物した『寄席放浪記』(廣済堂出版刊)の中の「なつかしきチャンバラスター」と題したエッセイで、大都映画の筆頭時代劇スターの阿部九州男は「晩年の悪役の方が似合う。どう白く塗っても、少年ファンを魅くアイドルにはなりにくい」が、近衛は「なかなかの美剣士で、大都映画でも屈指の人気があった」といっている点は非常に重要である。 つまり近衛は、人気という一点に限れば、阿部、海江田、松山を凌駕していたといっても過言ではないのである。 衆知のように、戦前から昭和の末期までは、ブロマイドの売り上げがスターの人気を計るバロメーターになっていた。 そして、昭和十一年から十五年までの総合売り上げベストテンは 第一位 原節子 第二位 桑野通子 第三位 近衛十四郎 第四位 佐分利信 第五位 霧立のぼる 第六位 水戸光子 第七位 水島道太郎 第八位 轟夕起子 第九位 宮城千賀子 第十位 高山広子 となっている。 この間、昭和十一年三月に公開された十二本目となる主演作『北時雨恋の旅笠』(監督 大伴龍三)の撮影終了後、昭和十四年まで、応召によって新潟の新発田歩兵第十六聯隊へ赴任し映画界を離れていたことが近衛のブロマイドの売れ行きに拍車を駆け、その結果、総合ベストテンの第三位についたとも考えられるが、いずれにしても、この事実は「近衛は大都映画でも屈指の人気スターだった」という阿佐田哲也の話が信の置けるものであることを裏付けているのは間違いない。 ちなみに昭和十一年には、海江田譲二も今井映画へ移籍していることから、大都映画では二つの大きな穴が空いた形となり、それを埋めるため松竹から大乗寺八郎、全勝キネマから杉山昌三九がそれぞれ入社し、スターとして売り出されてゆく。 しかし、それでも近衛の人気が陰りを見せることはなかった。 昭和十二年には、応召で新発田歩兵第十六聯隊赴任へ赴任しているにもかかわらず無理やり東京に呼び戻され、オールスター作品の『忠臣蔵』(昭和十二年三月公開。監督 白井戦太郎)に、赤穂浪士に加担した疑いで幕府の役人に捕らえられ拷問を加えられるも、「天野屋利兵衛は男でござる!」と言って口を割らなかった侠商天野屋利兵衛役で出演。 そして昭和十四年に新発田歩兵第十六聯隊を除隊し、三月に公開された『真田十勇士 前編』(監督 石山稔)の真田大助役で大都映画へ復帰したあと、大都映画がなくなる昭和十七年までの約三年間に十九本もの主演作品を撮り、大乗寺八郎とはライバルとして激しい火花を散らすのである。 復帰後の近衛の主演作で特筆すべきものに、吉川英治の小説『宮本武蔵』にある般若野の闘いを映像化した、佐伯幸三監督の『決戦般若坂』がある。 これは戦時下の昭和十七年二月に公開された大都映画最後の作品で、奈良県での大ロケーションを敢行し、筆頭時代劇スターの阿部九州男をはじめ、水川八重子、本郷秀雄、クモイサブロー、大乗寺八郎らほぼオールスターといっていい顔ぶれの出演によって製作されたのだが、映画評論家の故深沢哲也は 「小品ながら捨てがたい味があった」 とこの作品を評し、また永田哲朗氏は『歴史読本』において、 「近衛の宮本武蔵は荒々しく、立回り場面も、大映で伊藤大輔が片岡千恵蔵の武蔵で撮ったものより見応えがあった」 と、こう述べていることを付記しておく。 |
|
| 新潟の新発田歩兵第十六聯隊を除隊後、昭和十六年に大都映画のスター女優だった水川八重子と結婚し、主演スターとしても以前にも増した活躍をしはじめていた近衛は、正に順風満帆たる役者人生を歩んでいたといっていい。 だが、昭和十七年一月に、新興キネマ、大都映画、日活製作部門の合併による大映の発足と時を同じくするように二十八歳の若さで「近衛十四郎一座」を旗揚げし、映画界に見切りをつけ、実演に走る。 この、近衛が実演に走った理由について触れられたものに、唯一永田哲朗氏の『殺陣』があり、このように記されている。 十七年一月に大都は日活、新興と合併して大日本映画(大映)が生まれる。 そして、阪妻、千恵蔵、右太衛門、寛寿郎のいわゆる“剣戟四大スター”が結集した。 当然、近衛らの出る幕はないわけで、しかも製作本数は激減し、娯楽ものは作らなくなっていたから、彼もほかの多くのスターと同様、映画界に見切りをつけ、実演に走った。 永田氏がこの拠りどころにしているのは、『週刊大衆 昭和四十二年十月二十六日号』に掲載された、近衛と松方弘樹父子へのインタビュー記事“人物接点”(中村半次郎さま提供)ではないかと思われる。 なぜならば、この中で近衛本人が 「(大映には)四大スターというのがいてね、これじゃ僕に番は回ってこないと思って実演に走ったわけです」 と、こう語っているのである。 概に述べたように、大都映画は同業者や評論家から「粗製乱造、三流」などと酷評された、合併された三社の中では最も格の低い映画会社であり、さらにまた、円熟の域に達している大スター阪妻らといまだ二十代で二線級のスターだった近衛にも、歴然たる核の違いがあった。 これらの観点に立つ限り、大映で近衛の出る幕がなかったというのも、一応うなずける話ではある。 だが私自身は、大映で近衛の出る幕はじゅうぶんにあったと見ている。 昭和十二年七月七日、日中戦争が起こり、これが十六年十二月八日の太平洋戦争にまで発展する。 この戦時体制突入のため、映画界は、いちじるしい変貌を強いられた。 十四年四月に映画法が公布され、十月から実施されたが、この結果、映画は国民に対する宣伝機関として、情報局、つまり軍部の統制下に置かれることとなる(『殺陣』)。 そして、重要な軍需品のひとつと見なされていた生フィルムの欠乏という事態もあり、昭和十六年八月、情報局は“社団法人大日本映画協会”に、中小プロダクションを含めて十社あった映画製作会社を二社に統合するよう申し入れた。 情報局の二社案を映画界の現況に照らせば、日活は和議法にもとづく和議会社で合併は不可能であるから、松竹と東宝を中心とした統合が妥当なのだが、その後、情報局が三社案も検討するという態度を示したために、会社間で意見対立が起きた。 松竹は松竹、東宝の二社案を主張し、東宝は原則二社であるが、三社でも可という姿勢を示した。 新興キネマは、前に述べたように松竹系であり、合併となれば松竹へ吸収され消滅してしまうため、専務取締役の永田雅一は、新興キネマ、大都映画、日活の対等合併による新会社設立という案を持っていた。 これらの案に対し、日活の堀久作は、新興キネマは松竹、他の中小プロダクションは東宝と統合し、日活が大都映画を吸収して新会社を設立すべきであると進言した。 だが永田は、「情報局は、局の指令に従って動く半官半民会社を第三会社として持つべきである」と、あくまでも新興キネマ、大都映画、日活の対等合併を主張。 さらに松竹の大谷竹次郎が、自らが所有する新興キネマの株を大都映画に売却してもよいと言い出したことで、新会社設立における松竹の影響力は回避され、結果、情報局も永田案を指示することとなったのである。 しかし先に触れたように、日活は和議法にもとづく和議会社だった。 昭和初期より業績が悪化し、経営権の争奪戦が勃発。 松竹、東宝両社が株式の相当数を抑え、かつ両社から一定数の重役を迎えている状態だったのである。 そのため統合は円滑に進まず、最終的に日活は撮影所と設備を現物出資として新会社に提供。 これにより新興キネマ、大都映画、日活製作部門から成る大映が設立され、日活は興行会社として残ったのである。 大映発の足後、永田雅一はしばらく社長を置かず、昭和十二年に死去した大都映画の社長河合徳三郎の養子である河合龍斎とともに専務取締役へと就任し、この二専制によって会社を運営した。 昭和十八年に文藝春秋の菊地寛が社長に据えられて以降も、終戦後に永田と河合がパージにかかるまで、この運営方法が変えられることはなかった。 そして、昭和十七年十一月に公開された田中重雄監督、宇佐美淳(淳也)主演による『香港攻略 英国崩るるの日』のような国策映画を作るいっぽう、阪東妻三郎の『伊賀の水月』(昭和十七年八月公開。監督 池田富保)や片岡千恵蔵の『歌ふ狸御殿』(昭和十七年十一月公開。監督 木村恵吾)などの大衆娯楽作品も積極的に製作したが、新興キネマと大都映画には娯楽時代劇を製作するノウハウが蓄積されており、大衆娯楽作品を製作することで、両社の観客層を取り込もうとしたのだと思われる。 だから、阿部九州男は準大物として時代劇でずっと渋い二枚目を演じ、琴糸路は阪妻、寛寿郎の相手役という破格の待遇で迎えられ、水島道太郎も現代劇のスターとして活躍することが出来たのであり、大都映画ではこの三人に勝るとも劣らない人気があった近衛の出る幕も、当然あったと考えられるのである。 いささか贔屓の引き倒しに過ぎるかも知れないが、私は、昭和十一年か十五年までの近衛のブロマイドの売り上げが、上原謙、佐野周二と“二枚目三羽烏”を結成し、女性客が映画館へ殺到したと云われる松竹現代劇の二枚目スター佐分利信のそれを凌いで総合ベストテンの第三位に着いたこと。 そして、まだ二十代で伸び盛りの青年俳優だったことからすると、もし大映に残っていれば、大友柳太郎や戸上城太郎のように主演映画を撮る機会もあったとさえ思っている。 だが、近衛は大映には残らず、実演に走った。 しかも 「(大映には)四大スターというのがいてね、これじゃ僕に番は回って来ないと思って実演に走ったわけです」 と、こう語っている。 これは間違いない事実なのである。 しかしここで留意しなければならないのは、近衛が大映の発足と時を同じくするように映画界に見切りをつけ、実演に走っているという点である。 つまり、大映に半年ないし一年在籍していた時期があり、その間にまったく映画出演が無く、これによって「四大スターがいるから自分に番は回って来ないだのだろうと思って実演に走った」というのであれば話はわかる。 が、実際には、近衛は大映に在籍していた時期がまったく無いに等しいわけで、そんな彼に、たとえ“剣戟四大スター”が結集したとはいえ、早い時点で何故「僕に番は回って来ないと思」えたのかが疑問なのである。 したがって近衛には、大映が正式に発足する前後に、自分に出番は無いと思わざるを得ない大きな出来事があったと、このように見るのが現時点では最も自然であるように思われる。 |
|
| 近衛が脳出血のため六十三歳で死去したのは、私が高等学校を卒業した年、すなわち昭和五十二年五月二十四日である。 昭和四十年にスタートし、コンビを組んだ品川隆二との軽妙な掛け合いが大うけした連続テレビ時代劇『素浪人月影兵庫』にはじまる近衛の“素浪人”シリーズ。 この第二弾で、同じコンビにより製作された『素浪人花山大吉』の放映が、近衛の持病である糖尿病の悪化により、昭和四十五年十二月に百四回で打ち切られて七年後のことだった。 とはいえ、読売新聞に掲載された訃報記事が、一時は「お化け番組」といわれたほどの高視聴率をはじきだし、茶の間を大いに沸かせた時代劇に主演したスターのものとはとても思えない、社会面のいちばん下、しかも一段組みと非常に小さい扱いだったのに対して、私は言い知れぬ寂しさを感じたことを今でもハッキリと覚えている。 だがこの後、スポーツ紙や女性週刊誌には、ゴシップを含めた近衛に関する記事が連日載った。 そしてその一誌に、近衛がまだ若いころ、ある会社からあった新選組副長土方歳三役での映画出演依頼を断ったというような話が掲載されているのを私は目にした。 そこには 「新選組の土方歳三、たしかそんな役をいただいたんです」 という近衛本人の言葉もあった。 だが、この製作会社や作品の題名、更に断った理由などについてはまったく言及されていなかったと記憶している。 しかしこの逸話は、近衛の四十数年に及ぶ芸歴を綴った記事の中で紹介されていた。 したがって彼がある重大な転機を迎えた時期の出来事だったはずで、近衛に土方歳三役での出演オファーがあった映画というのは、大映(大映となるのは文藝春秋の菊地寛を社長としてむかえた昭和十八年で、これ以前は大日本映画製作株式会社というのが正式な社名なのだが、便宜的に大映)の『維新の曲』(監督 牛原虚彦)だったのではないかと私は推測している。 この『維新の曲』は、戦時下の昭和十七年五月に公開された大映の記念すべき第一回製作映画で、新選組の池田屋斬りこみを発端に、蛤御門の戦い、薩長同盟、寺田屋事件、大政奉還、坂本龍馬・中岡慎太郎の暗殺を経て鳥羽伏見の戦いへといたる激動の幕末を描いた大作であり、当時いくつか作られた国策映画のひとつといっていい。 そして出演者も、阪妻(坂本龍馬)、千恵蔵(西郷吉之助)、右太衛門(桂小五郎)、寛寿郎(徳川慶喜)をはじめ、阿部九州男(近藤勇)、羅門光三郎(中岡慎太郎)、戸上城太郎(杉山松助)、大友柳太郎(佐々木只三郎)、加賀邦男(三吉慎蔵)、南條新太郎(沖田総司)、尾上菊太郎(吉田稔麿)、澤村國太郎(松平容保)、琴糸路(沖田の恋人あき)、市川春代(お龍)など、大映の前身である日活、新興キネマ、大都映画の主だったスターが一同に会した、第一回製作映画にこの上なく相応しいものだった。 ちなみに南條新太郎とは、勝新太郎と近衛の壮絶な対決が話題となった『座頭市血煙り街道』で、御禁制の塗物作りにかかわる職人と思しき一団を引き連れて旅をする、目つきの鋭い男を演じた俳優である。 そして土方歳三は、今は亡き悪役俳優・田中浩の実父である寺島貢が演じていた。 ところが、大都映画の筆頭時代劇スターだった阿部の演ずる新選組局長近藤勇が、当時としては珍しく、あくまでも儀を貫き病に冒された沖田とその恋人あきの関係を温かく見守る二枚目として描かれていたのに対し、土方は副長とはいいながら、ほんの数シーンで一瞬顔が映されるだけの台詞が一言もない、その他大勢の隊士のひとりというような扱われ方しかされていないのである。 つまり、事実、近衛に土方役での出演依頼のあった映画が大映の『維新の曲』だったとすると、彼がそれを断ったのは仕出しの俳優でもつとまるような端役だったからだと考えられる。 そして、近衛が端役をやらされても致し方ない事情があった。 とはいっても、それは大映に“剣戟四大スター”がいたからでは決してない。 大映内での日活系と新興キネマ系との対立である。 映画『維新の曲』のシナリオを書いた脚本家の八尋不二は、自身の脚本家人生を綴った『百八人の侍―時代劇と45年―』(朝日新聞社刊)という著作において、伝統が古く、版妻、千恵蔵、寛寿郎の三大スターを擁して時代劇界に覇を唱えていた日活は、右太衛門が一枚看板だった新興キネマや三流とまでいわれていた大都映画と合併されることに根強い不満を持っていた。 そのため、情報局を握って勢いづく永田雅一に対し、日活の京都撮影所長だった曽我正史は、表面和を装いながらも、裏面では隠微なレジスタンスをやり、合併はスムースに進捗せず、大映の発足後はとりわけスタッフの融和が容易ではなく、これが日活系と新興キネマ系の対立に発展。 これにより『維新の曲』製作まえに木屋町の料亭で持たれた日活系と新興キネマ系の顔合わせも、阪妻、寛寿郎が出席しないなどで非常に白け、この暗流が障害となって『維新の曲』を監督した牛原虚彦はたちまち憔悴し、作品の出来も芳しくなくそれはどヒットしなかった。 そして、この日活系と新興キネマ系の対立は長く尾を曳き、戦後、大映に「日映騒動」が起こり、河合龍斎の死去によって専務取締役を引き継いだ曽我正史らの大量脱退を見るに至ったのも、「遠因は概にこの時に胚胎していたので、淵源するところ遠く、且つ深いと知らなければならない」と述べている。 八尋のいうように、歴史と伝統をほこる日活が、格下である新興キネマに膝を屈することを潔しとせず、これが大映の発足後に対立にまで発展した原因のひとつであることは間違いない。 だがしかし、日活系と新興キネマ系の対立が生まれた最大の原因は、合併を主導した永田雅一本人にあったと見るべきだろう。 もともと永田は日活の総務、製作、脚本部長だったのだが、社長とそりが合わず、大勢のスタッフと俳優を引き連れ、昭和九年に第一映画を設立。 昭和十一年に同社が解散すると、その後は松竹の大谷竹二郎の知遇を得て、彼が経営する新興キネマの専務取締役兼京都撮影所長へと就任する。 しかし、新興キネマの専務取締役兼京都撮影所長の職は第一映画が解散する前から約束されており、そもそも第一映画の資本自体が松竹から出ていた。 つまり、永田は松竹をバックに経営難に陥っていた日活を分裂させようと動いていた可能性が高く、大映の発足後に日活系と新興キネマ系の対立が起こったのは当然の成り行きだったと言っていいのである。 大映の正式な発足後、会社の実権を新興キネマと大都映画が握ったことも日活系にとっては看過できない問題で(専務取締役に就任したのが永田と大都映画の河合龍斎だったことは先に述べたが、常務にも新興キネマの六車修と大都映画の鶴田孫兵衛が就いた)、対立をより険悪なものへ発展させたと思われる。 この大映における日活系と新興キネマ系の対立は、当然、製作される映画の配役を巡っても起こり、それがもっとも激しかったのは、当時の人気スターのほとんどが集まった時代劇においてだったはずである。 つまり、主な登場人物の配役が日活、新興キネマの俳優によって決められ、その結果、三流というレッテルを貼られていた大都映画の俳優たちは、筆頭時代劇スターだった阿部九州男を除いて大部屋並みの扱いしかされないようになる。 これによって近衛は『維新の曲』で端役である土方歳三を演らされる羽目になった。 だが本人は、これを日活系と新興キネマ系の対立のためではなく、阪妻、千恵蔵、右太衛門、寛寿郎がいるからだと思った。 そのために、近衛は 「四大スターというのがいてね、これじゃ僕に番は回ってこないと思って実演に走ったわけです」 と語っているのだとすれば、『維新の曲』の撮影がクランクインした昭和十七年二月。 それかから逆算すると、近衛に土方役での出演依頼があったのは、遅くとも同年の一月だったはずで、大映が発足してすぐの時点で、なぜ「(大映には)四大スターというのがいてね、これじゃ僕に番は回ってこない」などと判断でき実演に走ったのかという、最大の疑問は解消されるのである。 ただし、現時点ではあくまでもその可能性があるというに過ぎないのだが。 大都映画の時代劇で主演を張ったスターでは、杉山昌三九と大乗寺八郎も大映には残らなかった。 杉山は、昭和十六年八月に公開された『逢魔の辻』(監督 佐伯幸三)へ主演したのを最後に最も早く大都映画を離れ実演に走っているが、全勝キネマで主演スターとして一本立ちする前に日活、新興キネマにおり永田雅一を直に知っていることから、彼の主導によって設立される新会社に前途多難を想ったのかも知れない。 いっぽう、近衛の最大のライバルでもあった大乗寺は、戦後、数本の時代劇へ端役で出演したのち、昭和三十二年に四十七歳で死去した。 また、大都映画で剣戟スターと監督の二束の草鞋を履いていた松山宗三郎は、小崎政房の名で監督として大映の多摩川第一撮影所に移動した。 しかし、井染四郎主演の『思出の記』(昭和十七年八月公開)と宇佐美淳主演の『女のたたかひ』(昭和十八年一月公開)を撮った後に大映をやめる。 そして、近衛の育ての親と言ってもいい白井戦太郎も、大映で池田富保監督のB班の監督をやり、昭和二十年一月に公開された片岡千恵蔵主演の『龍の岬』を演出後に応召。 田坂具隆監督の上官として広島聯隊へ赴任したが、八月六日の原爆投下に遭遇し、戦死した。 |
|
| 近衛は大映が発足するのと時を同じくするように、多くのチャンバラ映画ファンを魅了していた剣戟スターから一転し、劇団の座長になった。 彼の一座はかなりの大所帯で、最も多い時には座員数五十人から六十人をかぞえたことがあったという。 余談ながら、松竹歌劇団にいた高城富久子という踊り子が、昭和十五年に大都映画から美空ひばりの芸名で女優デビューした。 彼女は有名な歌姫・美空ひばりと区別するため、特別に「初代」という語を冠して呼ばれる。 そしてこの美空ひばりは、近衛の取り持ちによって同じ大都映画の香取栄二という俳優と結婚したのだが、彼も座員として近衛一座に加わった。 この後、近衛は十年という、一座を組んだ時代劇スターの中では最も長い期間を実演で過ごすことになり、私は冒頭で、彼が最後まで実演に残ったのは、自身のある重大な決意がそうさせたのだと述べた。 その重大な決意というのは、現時点ではこれも推測の域を出ないのだが、こういうことだとだったのではないかと思う。 この当時、一座を旗揚げして巡業した時代劇スターは、近衛だけではない。 戦争の影響による映画製作本数の削減で、活躍の場を失った中堅時代劇スターの多くが一座を結成して巡業をしたのだが、戦争が終わると、ぞくぞくと映画界へ復帰してゆく。 つまり、彼らにとって実演をは映画が復興するまでの一時的な腰掛程度にしかなかったのである。 しかし近衛には違う。 かれは一座を独立プロダクションにに育て上げ、自分で映画を作ろうと決意をし、その目途が立つまでは映画へ戻るつもりはなかった。 そして、元来が剣戟スターであるだけに、手始めとしてまず、これまでにない本格的な立回りを一座の売り物にしようと考え、そのために、座員と正に血の滲むような激しい殺陣の練習を繰り返したのであり、このように決意をするに至ったのは、理由はなんであれ、大映で自分などの出る幕はないという厳しい現実を突きつけられたからではないかと私は見ている。 では、そうまで決意をした近衛は、なぜ独立プロダクションの設立という思いを果たせぬまま、最終的に単独で映画界へ戻ることとなったのか? これについて述べるには、まず、戦中戦後に、剣劇と近衛一座がおかれていた状況を見なければならない。 “剣劇”というジャンルを開拓し、立回りを意味する「タテ」という言葉に「殺陣」の字を当てたのは、新国劇の澤田正二郎である。 大正六年四月、東京の新富座で行われた新国劇の旗揚げ公演は無残な失敗に終わり、六月の京都南座公演も東京以上の不入りだった。 ところが、七月の大阪道頓堀角座では、座付き作者仲木貞一の『家門の犠牲』で見せたテンポの速い立回りが受けたことから、そういう剣戟場面を取り入れた芝居が企画されることになる。 そして、その路線を決定づけたのが、大正八年から座付き作者になった行友李風作『義人国定忠治』の成功で、これによって関西に確固とした地盤を築いた新国劇は、同年六月、念願の東京進出を明治座で果たしたのだが、十一月になって、名古末広座で『国定忠治』を上演中に、中田正造、小川隆、伊川八郎、小笠原茂夫らの幹部役者が分裂し、新声劇に入る。 新声劇はその年の九月に道頓堀弁天座で旗揚げされた新派の劇団だったのだが、中田、小川らの加入で関西における剣劇の一大勢力となり、この新声劇から、戦後は東映時代劇の脇役として知られる明石潮が国粋劇を結成して独立し、大正十四年に浅草観音劇場へ進出。 さらに明石に対抗するように、同じ新声劇から酒井淳之助が剣劇文芸団を結成して公園劇場へ打って出て以降、浅草にはいろいろな剣劇一座が族生し、「浅草が剣劇一色に塗りつぶされた」とまでいわれる隆盛を極めることになるのである。 ちなみに、いっとき新声劇から独立していた伊川八郎の国精劇にいた河部五郎が、日活に入ってチャンバラ映画のスターになった。 また、新国劇の創立から澤田正二郎の片腕として働いてきた倉橋仙太郎は、大正八年に病を得て故郷の大阪南河内に帰ったが、震災後に新民衆劇学校を作り、その生徒たちが第二新国劇として大正十四年夏に、浅草観音劇場で旗揚げ公演をした。 原健作(のちに健策と改名)、室町次郎らがその中心だったが、室町は翌十五年に日活へ入り、大河内伝次郎となる。 さしもの剣劇も昭和に入るとさすがに下火になり、族生する群小劇団は淘汰され消え去ってゆく。 とはいえ、隆盛期からすこし遅れて登場した梅澤昇(梅沢富美男の父梅沢清の師匠でのちに龍峰と改名)や、第二新国劇時代に金尾修を名乗っていた金井修などは依然として根強い人気があった。 さらに昭和十年代に入ると、籠寅こと保良浅之助育てた女剣劇が隆盛を極め、不二洋子と二代目大江美智子の大看板をはじめ、伏見澄子、富士嶺子、初代筑波澄子、巴玲子、近衛八重子らが浅草を席捲した。 そして昭和十七年から十八年にかけて、戦争の影響による映画製作本数の削減で、近衛のほかにも、海江田譲二、杉山昌三九、本郷秀雄、坂東好太郎、澤村國太郎、尾上菊太郎、青柳龍太郎、浅香新八郎といった時代劇スターがそれぞれ一座を結成したため、顔ぶれはいっそうにぎやかになったのである。 ところが、映画の製作と興行に規制が加えられたように、徹底されるまでには至らなかったものの、剣劇も時局に順応した筋立てのものを出し物とするよう求められ、これによって官憲の目が常に光っている浅草を離れる一座が多くあらわれた。 近衛一座もそのうちのひとつで、実演時代のほとんどを地方巡業に費やすこととなるのである。 近衛は一座を率いて、日本全国津々浦々を回った。 しかしこれまでのところ、その足跡は極くわずかしか明らかになっていない。 そのうちのひとつ、岩手県北東、青森との県境に近い二戸郡一戸町に現在もある萬代館は、戦中戦後を通じ近衛一座が何度も公演した映画館で、まだ赤子だった松方弘樹が、近所の女性に貰い乳をしていたという微笑ましいエピソードが残されている。 また『近代歌舞伎年表京都編 別巻』には、次のような近衛一座の公演記録が載っている(じゅうよっつさま、中村半次郎さま協力)。 ○三友劇場 昭和十八年六月一日〜(五日は休業) 平日正十二時開場 昼夜二回 水川八重子・近衛十四郎大一座 京都初公演 土田新三郎作・演出 [第一]時代劇 宮本武蔵―乗寺の決闘― 五場 平山晋作 [第二]現代劇 ふるさとの風 二場 神田伯山口演 近衛十四郎十八番物 [第三]時代劇 次郎長外伝―森の石松― 四場 ○三友劇場 昭和十八年六月九日〜(十五日) 平日正十二時開場 昼夜二回興行 水川八重子・近衛十四郎大一座 [第一]続宮本武蔵―血風巌流島― 五場 土田新三郎作 [第二]幕末婦系図 四場 平山晋作 [第三]勘太郎月夜唄 五場 ○三友劇場 昭和十九年三月一日〜 平日正午開場 新同志座 葉村俊二作 [第一]時代劇 宮本武蔵―二刀流開眼― 一場 陸軍記念日作品 神田良一作 [第二]現代劇 征け北太平洋 一場 近衛十四郎・水川八重子ほか 栗島狭衣原作 滝井止水脚色 近衛十八番の内 [第三]時代劇 信州路の忠治 三場 ○三友劇場 昭和十九年三月十一日〜(十七日は休場) 平日正午、日曜十一時開場 新同志座 村上浪六原作 土田新三郎脚色 [第一]時代劇 喧嘩長屋 四場 斯波馬太策 [第二]現代劇 子は鎹 三場 近衛十四郎・水川八重子ほか 白井戦太郎作 [第三」時代劇 海援隊 四場 ○三友劇場 昭和十九年三月二十日〜二十九日(二十二日は休場) 平日正午開場、日曜祭日前十一時開場 新同志座 御名残り 白井戦太郎作 [第一]時代劇 飛騨のかけ橋 四場 土田新三郎作 [第二]現代劇 まごころ 一場 近衛十四郎・水川八重子ほか 小倉貴男作 [第三]時代劇 金四郎功名録 この、近衛一座の三友劇場での公演記録を見ると、昭和十八年にはまだ上演されていた任侠物と剣豪物が十九年になるとまったく姿を消し、勤皇倒幕物や軍国物が多く出し物とされているのがわかる。 おそらくこれは、時局柄好ましくないとして、股旅物をふくめいわゆる任侠の徒を主人公にした演目の上演が禁止され、合わせて立回り場面の制限、自粛が徹底されたということなのだろう。 近衛はこの後、昭和十九年三月の京都三友劇場公演後のことと思われるが、二度目の召集により朝鮮の羅南と満州の延吉で一年八ヶ月を過ごす。 そのため復員するまでの間、一座の座長は、妻であり元大都映画のスター女優だった水川八重子が代わってつとめた。 |
|
| 近衛が満州から復員したのは昭和二十一年の十月だった。 ところが、敗戦国として終戦を迎えた日本は、占領軍によって統治されていた。 しかもその指導による軍国主義から民主主義への体制の変化の過程で 「封建的な忠誠と復讐の教義にに立脚している歌舞伎的演劇は、今日では受け入れることはできない。叛逆、殺人、欺瞞といったことが大衆の前で公然と正当化され、法律にかわって私的復讐が許容されている限り、日本人は今後とも現在の国際社会を支配している行為の根本を理解することができないであろう」 ということになり、歌舞伎とチャンバラ映画の上演および上映が、占領軍の下部組織であるCIE(民間情報教育局)によって禁止されてしまった(歌舞伎に関しては、古典演劇としての特殊性が認められ、昭和二十二年に上演が許されている)。 この厳しい措置によって、時代劇スターたちは現代劇への転向を余儀なくされるのだが、時代物への禁忌条項は映画、演劇ばかりでなく小説にも課せられた。 要するに占領軍は、時代劇のあだ討ち物などで、日本人が戦勝国への復讐心を掻き立てることを恐れたのである。 剣劇は映画とくらべて影響力は少ないと思われたのか、検閲はいくらか緩やかで、上演禁止処分を受けるまでには至らず、当初は股旅物を出し物にすることも許された。 しかし仇討ち物に対しては厳しかったし、股旅物も、一宿一飯の恩義のために、恨みつらみもない相手に敵対して殺傷する封建的人間は好ましくないとして、間もなく上演が禁止されてしまう。 そのうえ、刀を抜いての立回りも三十秒以内に制限され、CIEの演劇課の担当者が劇場へ足を運び、立回りが三十秒を少しでも超えると奥役を呼びつけて戒告を与えた。 先に触れたように、太平洋戦争の末期には、映画の製作と興行に強い規制が加えられたのと同様に、剣劇も時局柄好ましくないとして股旅物などの上演が禁止された。 そのために、多く勤皇倒幕物や軍国物が出し物とされ、剣劇そのものが本来の魅力を失っていた。 さらに昭和十九年三月に、浅草六区の興行街では、防空法による木造建築の強制疎開がお行われ、実演劇場では公演劇場、昭和座、オペラ館が取り壊されて空き地とされたばかりでなく、昭和二十年三月の東京大空襲で浅草一帯は焼け野原となる。 そして今度は占領軍によって立回りが封じられたわけで、剣劇にとっては正に命を奪われたに等しかった。 建物の強制疎開や空襲によって多くの劇場が失われた浅草で、戦争末期に実演の常打ち劇場となった常盤座では、昭和二十年の十二月までは元大都映画の時代劇スターである杉山昌三九と本郷秀雄の合同、梅澤龍峰、二代目梅澤昇一座、大江美智子一座が交代で公演を続けた。 しかし二十一年になると、一月の前半が大江美智子、一月の後半から金井修が出演したあとは軽演劇に本拠を明け渡し、二十三年には剣劇はまったく姿を消してしまう。 さらに、金龍劇場が昭和二十一年にロキシー映画劇場になったのを皮切りに、二十三年には大江美智子、嵐寛寿郎、坂東好太郎が出演したのを最後に松竹座が、そして翌る二十四年には花月劇場が次々と剣劇に見切りをつけて映画館へ転向してゆくというように、CIEによる時代物の検閲は、戦後の浅草の剣劇地図を、戦前戦中とは大きく変えてしまったのである。 近衛の長男である松方弘樹は 「復員後の親父は終戦後のゴタゴタで仕事がなく、川口のオートレース場に通っていた」 と言っているが、当の本人とすれば、立回りが封じられた状況で何を出し物にしたらよいのかわからなかったろうから、それも致し方なかったのである。 いっぽう、一座を結成していた時代劇スターたちは、実演劇場が次々と映画館へ鞍替えしていったことでぞくぞくと映画界への復帰をはたしてゆき、世話物や現代物など、演目の幅が広くない既存の一座も、都落ちをするようにCIEの目が光っている浅草を離れていった。 そして近衛も、「座して死を待つよりは」という覚悟で地方巡業から一座の公演をはじめるのだが、北海道で、後の“デン助”こと大宮敏充と出会い、公演の便宜を図ってもらっている。 戦前からコメディアン兼劇作家として浅草で活躍していた大宮は、召集によって北海道へ送られ、終戦後に小樽で除隊。 この後しばらくの間、妻と小樽で暮らしていたのだが、近衛一座の公演の便宜を図った様子を『デン助 浅草泣き笑い人生』(三笠書房刊)という著作の中で次のように語っている。 (前略)ある日、突然、MPがジープで乗りつけ、ぼくは引っぱられ、札幌へ連れて行かれちゃった。 MPが取り調べにやってきて、「キミは劇作家だったろ、かいてたろ」って、言うんですよ。 日本語のやけにうまいヤンキーでした。 ぼくの前に調べられたやつは、よしゃあいいのに、 「アメリカの方には、分からないけど、日本古来の歌舞伎っていうものから、発想しましてですね・・・」 とか、能書きを言った。 すると、彼は、 「あなた、そういうこと言ってもね、私ね、日本の明治、大正時代の文豪の作品、よく読んでます。歌舞伎、よく観てますよ」 と言われて、彼は、出鼻をくじかれちゃって、グーもスーも言えやしない。 で、そいつら、逆にあとへ残されちゃった。 ぼくの番がやってきて、 「あんたは、戦争中、戦争鼓吹するような本を書きましたか」 っていうから、こっちは、もう、覚悟しちゃって、 「書きました」 「どうして書いたんですか」 「国家の方針がそこにあったから、したがって、書きました」 「いま、どうですか」 「え、もう、いまは、平和。え、いまはもう平和。友愛の精神をもって、平和を鼓吹するようなものを書くつもりでおります」 そのとき、軍曹ぐらいの男が出てきて、あなたの答えは、正直でよろしい、これ読みなさい。 といって、マッカーサーの名の入った十六条か十七条くらいの項目が書いてある文書をくれた。 それには、たとえば、故なくして人を斬ることはいけない、人身売買はいけないとか、これに抵触するようなことを書いてはいけない、とある。 「私は、そういうことはいたしません」 と誓って、ようやく釈放された。 あと、能書きを言ったやつは、みんなひっかかっちゃった。 それ以来、その軍曹とスッカリ仲良くなってしまった。 その後、近衛十四郎一座が、北海道を巡業して歩いていた。 ところが、もってきた狂言が「宮本武蔵」なんですね。 「宮本武蔵」は、近衛君の当り狂言でしたからね。 ところが、「宮本武蔵」は、その何カ条かの全部にひっかかるんです。 ひっかからないところはない。 あれだけ、故なくして人を斬ったりするのもないし、人身売買もあるし・・・、それに、そのはかの、「森の石松」「此野村大吉」というような芝居も、みんなあぶない。 それで、ぼくが、いちいちチェックして、仲の良くなった軍曹ところへ行き、 「これは、戦争中にやったもんで、こういうふうに訂正してやるようにしているが、ここんところで人を斬るのは、これをぬかすと、ここはどうしても話が続かないから、大目にみてやってくれ」 と、頼みこんで、ひっかからないように訂正した。 それで、ポンとハンコウ押させて、彼(近衛)に許可済の台本を渡した。 その晩は、彼と夜中の三時頃まで飲んで、気がついたら、往来の真ん中に寝ていて、腕時計を盗まれてしまった。 これも思い出です。 大宮の話からこれが札幌での出来事だったのはわかるが、いつごろのことだったのかについては言及されていないのでわからない。 しかし、彼は昭和二十三年に浅草へ戻り「デン助劇団」を旗揚げしていることから、おそらく昭和二十二年ごろの話だろう。 そして、すでに簡明に纏められている実演時代のプロフィールに、近衛一座と海江田譲二一座が函館の巴座で合同公演を行った時のポスターが載せられているが、これもこのころのことではないかと思われる。 |
|
| 二代目大江美智子の話によれば、刀を抜いて三十秒という立回りの制限は、昭和二十四年に解除されたという。 しかしそのような通達があったいうことではなく、うやむやになり解除された形になったのである。 このころはしかし、浅草では既存の実演劇場が次々と映画館へ鞍替えし、実演の刀を抜いて三十秒という立回りの制限がうやむやになり解除された形となったように、チャンバラ映画もなし崩し的にではあるが製作されており、復興する兆しをみせはじめている。 時代劇復興のエポックメーキングになったのは、昭和二十三年十二月に公開された長谷川一夫主演による新演技座映画『小判鮫』(監督 衣笠貞之助)で、占領軍が忌み嫌った復讐劇『雪之丞変化』をリメイクしたものである。 次いで二十四年五月には、阪東妻三郎と大河内伝次郎の両巨頭が顔をあわせる『佐平次捕物帳 紫頭巾』(監督 マキノ雅弘)が公開。 二十五年十二月には、大谷友右衛門主演の東宝映画『佐々木小次郎』(監督 稲垣浩)が封切られ、このころには、一座を結成していた時代劇スターのほとんどが映画界へ復帰しているが、近衛が映画俳優として再スタートを切るのは、これから三年後のことである。 そして、既存の実演劇場が軒並み映画館へ鞍替えしていく一方、ストリップ劇場も増えている。 ストリップの走りになったのは、昭和二十二年一月に開場した新宿帝都座五階劇場の「額縁ショウ」だといわれる。 第一回公演の『ビーナスの誕生』のなかで、中村笑子が名画の構図を真似てポーズをとった。 この時はまだ、ブラジャーをつけていたが、二月の第二回公演『ル・パンテオン』で、甲斐美晴がはじめて乳房をあらわにした。 しかし、当時はまだ、ヌードは動いてはいけないという決まりがあった。 この劇場で同じ年の八月に上演された空気座の田村泰次郎原作『肉体の門』の成功も話題になった。 三條ひろみが扮した娼婦ボルネオ・マヤが、仲間の掟を破ったとして、ロープで吊るされてリンチを受ける。 この場面で彼女がブラジャーをむしり取られる、露骨な官能場面が評判になり観客を引き付けたのだが、演出をしたのは小崎政房。 元大都映画の時代劇スター松山宗三郎である。 小崎が監督として大映に残り、現代劇の『思出の記』と『女のたたかひ』を撮ったあと大映をやめたということは前に触れた。 大映をやめたあと、彼は演出家として水の江瀧子の劇団たんぽぽに入り、昭和二十三に劇団空気座を設立したのである。 ここには有島一郎、田崎潤、左卜全らがいたが、数年後、小崎は近衛が映画へ戻る際にかかわりを持つことになる。 帝都座五階劇場の「額縁ショウ」につづいて、渋谷の東横デパート四階にあった小劇場で、ラナー多坂というダンサーがセミヌードのソロを踊り、最後にポーズを決めると、ブラジャーがはずれて乳房があらわれ、すぐに暗転になるというシーンを見せたが、これも大入りになった。 そして、二十三年二月の帝都座五階劇場の『思い出のアルバム』で、片岡マリが額縁から抜け出し、乳房を露出したまま踊りまわった。 これが、動いてはいけないと決められていたヌードが躍動をみせた最初である。 浅草でも、昭和二十二年六月の常盤座の森川信一座による喜劇『モッちゃんの若様とモデル』に、モデルに扮した桜真弓が裸で椅子にすわっている場面が登場した。 そしてメリー松原、ヘレン滝、福田はるみ、ヒロセ元美など、初期のストリップを代表するスターがぞくぞくと登場した。 ストリップの人気が高まるにつれ、都内の盛り場には次々とストリップ劇場があらわれたが、やはり浅草がいちばん多かった。 はじめは軽演劇の添えものとして登場したストリップショウが、たちまち芝居と肩を並べ、つぎには芝居のほうが添えものの地位に後退してしまう。 それもやがて姿を消し、ショウのあいだに挿まれるコントのかたちでしか生き残れなくなったのである。 こうした軽演劇の衰微のなかで、わずかに持ちこたえたのは女剣劇だった。 もっとも一座として単独公演ができたのは、戦前からの大看板である大江美智子と不二洋子だけで、あとの群小一座は演芸場かストリップ劇場で演目のひとつを受け持っていたのである(筑摩書房刊、森秀男著『夢まぼろし女剣劇』)。 当時の浅草には剣劇一座のほかにも、堺駿二・丹下キヨ子らの東京レビュー、桜むつ子・伴淳三郎の東京ロックショウ、のちに東映時代劇の敵役として有名になる山形勲・鈴木光枝らの文化座があり、また、戦前派としては榎本健一、古川ロッパが各々一座を率いていたが、いずれもストリップ攻勢の前に膝を屈した。 そればかりでなく、昭和二十五年三月には、実演の最後の城だった常盤座が映画館へ転向したことで、不二洋子や大江美智子さえ浅草から姿を消してしまい、剣劇の退潮は全国の盛り場にも波及していったのである。 このころ、近衛は山口組三代目・田岡一雄の世話で四国を巡っていたようだ。 時節柄、劇場での公演ばかりでなく、入院中の傷病軍人の慰問や軍需工場への慰労も行ったかも知れない。 そして、永田哲朗氏の『殺陣』にはこう書かれている。 (昭和)二十四年ごろには、女剣劇に押しまくられてしまって、近衛も「水川八重子一座」と、女房の名前を看板に出さなくてはならない状態となった。 永田氏にしたがえば、四国は「水川八重子一座」を看板に巡業をしていた可能性もないとは言えない。 男を座長に頂く剣劇一座は、戦前、女剣劇が隆盛を極めていたころから人気に陰りが見えはじめていた。 そして、終戦後はストリップ攻勢にあって凋落の一途を辿ってゆく。 これは近衛が映画に戻ったのちのことだが、森秀男氏の『夢まぼろし女剣劇』には、次のような記述がある。 昭和初期から浅草で並び立った初代梅澤昇改め梅澤龍峰、二代目梅澤昇一座と金井修一座・・(略)・・梅澤一座は二十八年十二月に花月劇場で二代目襲名十周年記念公演をしたあと浅草から姿を消し・・(略)・・金井修も二十九年十二月に他の一座と合同出演したあとは、もう浅草に帰ることがなかった。 梅澤龍峰は、横浜の弘明寺のキャバレーを買い取って改装し、二十九年夏から梅澤劇場として開場したが、二代目梅澤昇が腰痛の悪化で舞台に立てなくなり、劇場の地の利の悪さも災いして客足が落ち、二年足らずで手放すことになった。 一座を解散した梅澤龍峰は、もとの梅澤昇に戻り、東映に入って時代劇映画の脇役をつとめたあと、京都の旅館の主人に納まった。 当然、近衛も梅澤、金井と同様の憂き目をみる軌跡を辿っていたと見ていい。 近衛の次男である目黒祐樹は、昭和三十九年九月に公開された近衛主演による東映映画『忍者狩り』で監督デビューをした故山内鉄也との京都映画祭での対談で、 「(地方巡業のときのこと)舞台が今みたいに良くなくて(舞台の表面が)ざらざらなのに、森の石松の芝居の最後の膝をついての十数分の立回りを、血だらけになって毎日やった」 と語っている(プロフィール『思い出話』 中村半次郎さま「京都映画祭」レポ2)。 おそらくこれは、昭和二十五、六年ごろの東京での公演の様子を語ったものだろう。 そして、血だらけになって立回りを毎日やっている様子から、近衛一座も傾いており、近衛はそれを立ち直らせるために懸命になっていたということを想像するのは、決して私だけではないだろう。 これ以外にも、近衛は一座を解散の憂き目にさらせないために色々な策を打っていたということは考えられ、「水川八重子一座」と看板を変えたということは大いにあり得る。 だとしても、「女剣劇に押しまくられてしまって、近衛も『水川八重子一座」と、女房の看板を出さなくてはならない状態となった」とするのは、果たしてどうだろう。 先に書いたように、剣劇のメッカである浅草では、ほとんどの一座がストリップの前に膝を屈し、わずかに持ちこたえたのが女剣劇だった。 もっとも、一座として単独公演ができたのは不二洋子と大江美智子の戦前からの大看板だだけであり、この二大看板さえ浅草から姿を消してしまう。 しかも、この剣劇の退潮は、すぐに全国の盛り場にも波及した。 つまり、女剣劇にも近衛一座を「押しまくる」という勢いはなかったわけで、近衛は、女剣劇だけがわずかに持ちこたえていたという、この一点に賭けて看板を「水川八重子一座」に変えたと、このように見るべきではないだろうか。 だが私には、今もって、近衛が「水川八重子一座」に看板を変えたということを確認できていない。 それに、水川八重子が大都映画のスター女優だったことからすると、そもそも「近衛十四郎・水川八重子一座」という看板で巡業し、昼夜二回に分けてそれぞれが主演する演目が掛けられたのではないかとさえ思っている。 したがって、近衛が「水川八重子一座」と看板を変えたのが事実か否かについては言及せず、その可能性だけを記すに留めておくことにする。 ただ、前に書いたように、近衛が傾いた一座を懸命になって立て直そうとしていたと思われるころ、なし崩し的にではあってもチャンバラ映画は製作されており、一座を結成していた時代劇スターもほとんどが映画界へ戻っている。 しかし、近衛が映画俳優として再スタートを切るのは、これからさらに三年後の昭和二十八年のことなのである。 この事実は、近衛にとって実演が腰掛ではなく、一座を独立プロダクションに育て上げ、自分で映画を作りつもりだったという傍証になると言っていいのではないかと思われる。 |
|
| さて、ここからいよいよ近衛が映画へ戻る決意をするに至る経緯を述べる。 が、それにはまず、浅香光代について語らなければならない。 昭和二十五年七月、松竹演芸場に浅香光代が初出演する。 浅香は昭和六年に東京の神田に生まれ、昭和十七年に、元新興キネマの時代劇スターである浅香新八郎一座に入り、小森昭子の芸名で初舞台を踏んだ。 十九年に浅香新八郎が亡くなり一座を解散してからは、青柳龍太郎、本郷秀雄の一座に加わった。 戦後は阪東鶴蔵の一座に入り、富士龍子と改名。 独立して一座を旗揚げしたときに浅香光代を名乗り、都内の小劇場や寄席を廻るうちに、十九歳で松竹演芸場に出演する機会を得た。 ストリップだけが勢いづいていた時期である。 「ストリップにまともに対抗するためには、やはりお色気でいかなければならない」(学風書院刊、浅香光代著『女剣劇』) そう決意した浅香は、初お目見えとなった松竹演芸場の舞台で、胸をはだけ太股が見えるくらいに着物の裾を捲って大立回りをやった。 あまりにも型破りな剣劇だったので、先輩たちからは邪道、ゲテモノなどと非難されたが、評判はたちまち広まり、これによって「ストリップ剣劇」という言葉も生まれ、朝霞が孤軍奮闘しているうち、昭和二十六年九月に花月劇場がふたたび実演劇場になり、大江美智子一座が出演した。 浅香は『女剣劇』において 「大江一座が花月劇場に出演したのは、何日まで待っても、ストリップ旋風の中で、孤軍奮闘の形だった私にとって、百万の味方を得たような気がした。やっと女剣劇が反撃にうつるチャンスが来たと思った」 と言っており、昭和二十六年十月二十二日付けの東京新聞も、『競演すさまじや女剣劇』と題して次のような記事を載せている。 目下浅草に出演中の中では、花月劇場の大江美智子一座が往年の映画スタア市川百々之助以下座員五十名を擁して、女剣劇の中でも一番の世帯を誇り、去る九月に一年半ぶりに上京したが、美ぼうと芸達者なので、家族連れのお客が多く、一ヶ月だけのつもりが開場前にお客が延々長蛇の列をつくるはどの大入り続き。 これに気をよくしてついに十一月いっぱいまでロングランし、十二月を休んで正月から又出演するといった物すごい人気。 他の一座は全部二十人足らずの小人数で、喜劇や色物、ストリップなどと抱き合せだが、その中では松竹演芸場の浅香光代が五尺三寸五分、十五貫の肉体美を自慢にストリップ剣劇で人気があり、続いて天龍座の富士嶺子は義太夫や新内をとり入れた歌舞伎剣劇。 百万弗劇場の大利根淳子のつやっぽい女剣劇、さる十七日からロック座に初登場の筑波澄子(初代筑波澄子の娘)のモロハダをぬいだりスソをまくったりする露出症女剣劇などまさに多種多様。 ストリップのファンには中年の男性が多いが、反対に女剣劇のファンには弱い女が大の男をバッタバッタと斬倒すのがお気に召すとみえて女性が多く、大江と浅香はプロマイドを場内で売っているが、女役よりも立役(男装)の写真のほうが圧倒的に売れている。 そうかと思うと「オヘソまる出しのストリップよりも、二の腕やモモをチラホラのぞかせてやる女剣劇のほうがかえってエロでいい」とやにさがっている男のファンもいて、「もっとまくれ」などと客席からぶしつけな大声をかけたりしている。 当時、松竹が淡島千景を、また、大映が京マチ子を主役にして女剣劇映画を製作したことで、人気にいっそう拍車がかかった。 しかし、男を座長に頂く剣劇一座は凋落の一途をたどっており立ち直ることができず、戦前からの名代である梅澤龍峰や二代目梅澤昇、そして金井修などが相次いで浅草を去ったことは先に書いた。 凋落の一途を辿っていたのは近衛一座も例外ではなかったことも指摘したが、ひょっとしたら、女剣劇がふたたび勢力を盛り返したことで「水川八重子一座」と、一座の看板を変えたのかも知れない。 だが、浅香光代は『女剣劇』において、 「昨日までのストリップショウに代わって、女剣劇が圧倒的な人気を博するようになったのは、ストリップショウに飽きかけた大衆が、女剣劇に新しい官能の刺激を求めて、続々と移動してきたからであった」 といい、さらに言葉を継いで 「私は戦前派とか、正統派女剣劇(不二洋子さんや大江美智子さんなど)と云われている人たちが上演してやるような、まともな女剣劇がやりたかった。が、私が、エロチックな女形をよして、立役の物を上演すると、お客の入りが悪かった。『浅香さん、あんたが立役をやってはいけませんよ。あんたは女形で売り込んだ人なんだから、あんたが立役をやると、お客の入りがね、どうも、・・・本社の人たちだって、あんたに立役をやらしちゃいけないと云ってるんだから、これからは立役はひかえるようにしてくださいよ』と、事務所の人に、こう云われると、私は不本意ながらも、戦後派的な女剣劇をやるより仕方がなかった」 という胸の内を明かしている。 そして、森秀男氏の『夢まぼろし女剣劇には次のような記述がある。 しかし、女剣劇が勢力を盛り返したといっても、ストリップとの綱引きは一進一退で、まだストリップのほうが優位を保っていた。 昭和二十七年一月に実演劇場になっやテアトル浅草は三月に公園劇場と改称したが、その演目に当時の事情がうかがえておもしろい。 新装開場の一月から三月までは、澤田清、大倉千代子、市川喜代子、巴玲子、水川八重子、近衛十四郎らの合同剣戟大会をやったが、不入りがつづいたため、四月からはロック座で有名だった筑波澄子とストリップショウの混成公演というかたちになった。 ここで森氏がいっている筑波澄子とは、『東京新聞』の記事で「露出症剣劇」と紹介されている浅香光代と人気を二分する新進のスターで、初代筑波澄子の娘である。 近衛はそして、この合同剣戟大会が不入りに終わったことで一座を解散し、映画に戻る決意をしたのだと思われる。 わたしは、現時点ではまったく推測の域を出ないながら、近衛は一座を独立プロダクションに育て上げ、自分で映画を作るつもりだった。 その手始めとして、まずこれまでにない本格的な立回りを売り物にしようと考え、これによって正に血の滲むような激しい殺陣の練習を座員と繰り返した。 つまり、近衛にとって実演は他の時代劇スターとは違い単なる腰掛ではなかったということをこれまで述べてきた。 そしてこのような一大決心をするに至ったのは、その理由は何であれ、大映で自分などの出る幕がないという現実を突きつけられたことに端を発しているということも触れた。 要するに、近衛にとって実演の舞台に立つということは、独立プロダクションを設立する資金集めの一環でもあったわけで、正当な剣劇が廃れてしまったということは、それをかなえる最大の術を失ったに等しいのである。 さらに元来が剣劇スターである近衛には、客に媚びてまで浅香の言う戦後派の剣劇をやることはできない。 端的にいえば、多くの劇団がそうであったように、近衛一座もストリップの前に膝を屈したのである。 これについては、 「(一座を結成していた時代劇スターたちは)戦後もみんな映画界へ戻ったけど、よし俺だけは実演で頑張ろうとやってたんですが、ストリップに負けたですね。なんといってもハダカは強いですな。それでやむなく単独映画界へ殴りこみですわ」(『週刊大衆 昭和四十二年十月二十六日号』掲載の“人物接点”より) と近衛本人が語っていることから、ほぼ間違いないと思われる。 しかし、正当な剣劇が廃れなければ、近衛もそう易々とは映画には戻らなかったろう。 これについては、近衛自身の話、とりわけ「やむなく単独映画館へ殴りこみですわ」という部分を玩味すれば、確かなものとして受け入れられるはずである。 そして、独立プロダクションが設立できたかどうかは措くとしても、近衛は実演で勇名を馳せていたのではないだろうか。 目黒祐樹の言葉を借りれば、たとえいっときであるにせよ、近衛の一座は、立回りの激しいことで評判になったのである。 近衛が映画へ戻る決意をした昭和二十七年には、占領軍によって上映禁止処分を受けていたチャンバラ映画の製作が大々的に解禁され、彼は八月に公開された、東横映画から改称して間もない東映と連合映画の提携作品『遊侠一代』に出演する。 これは吉良の仁吉(田崎潤)と、荒神山の出入りで仁吉に斬られる浪人門井門之助(大友柳太朗)とのかかわりを描いた映画で、監督をつとめたのが近衛とは因縁浅からぬ小崎政房(天辰大中と共同)だったのだ。 しかし、残念ながら近衛の演じた役柄等は不明である。 それほどに小さな役だったのだろう。 吉良の仁吉を描いた『叫ぶ荒神山』ではじめて主役を張った近衛が、同じく仁吉をメインに据えた『遊侠一代』で映画界復帰の第一歩を踏み出したというのも因縁めいた話だが、これに出演することになったのが自身の申し出によるものなのか、それとも小崎に促されたからなのかはわからない。 近衛はこの七ヵ月後の昭和二十八年二月に公開された大河内伝次郎主演の新東宝映画『名月赤城山』(監督 冬島泰三)に端役で出演したあと、綜芸プロの所属となり、正式に映画俳優としての再スタートを切る。 ちなみに近衛は、戦後の海軍軍人山本五十六と並ぶ故郷長岡の偉人、戊辰戦争で官軍に抵抗した長岡藩の家老河井継之助を主人公にした自主制作映画を掲げて映画界へ戻るつもりで、撮影にも入っていた。 とこるが、フィルムがまだ配給制だったり資金が集まらなかったりで(資金については仲間に持ち逃げされたという話もある)撮影は頓挫してしまい、文字通り裸一貫で映画界へもどっているのだが、映画俳優として正式に再スタートをきるまで七ヶ月ものブランクが生じているのは、この間に撮影をしていたからで、自分で映画を作るという思いだけは捨て切れなかったということなのかも知れない。 |
|
| 【補追】 本文でも指摘したように、一座を旗揚げしてから映画へ戻るまでの近衛にはいくつかの謎がある。 私がそれを感じはじめたのは、高校時代に三一書房からまだハードカバーで出ていた永田哲朗氏の『殺陣―チャンバラ映画史―』をはじめて読み、近衛が死去したあと、女性週刊誌で彼がまだ若いころ、実現には至らなかったものの新選組の土方歳三役である映画に出演が予定されていたという逸話を知り、その後、社会人になってビデオでリリースされていた大映の『維新の曲』を観てからである。 ちなみに三一書房版の『殺陣』には、現代教養文庫版では削除されている、大都映画時代の近衛と大乗寺八郎の噛み付き事件も載っていた。 それはさて措き、この『近衛十四郎の実演時代』は、そのいくつかの謎の解明を私なりに試みたものである。 今回、書いていてつくずく思い知らされたのは、近衛に関する資料の少なさである。 合わせて、浅草における剣劇の栄枯盛衰や女剣劇について詳しく記された専門書はあっても、男を座長に頂く一座や、戦後、地方の盛り場で剣劇がどのような状況に置かれていたかについて触れられたものがまったくないことにも唖然とする思いだった。 そのため、謎を解明したとはいいながら、ほとんどが推測で終始してしまい、地方巡業の様子には筆がまったく及ばなかったこと、これが非常に残念である。 ただし私としては、永田哲朗氏の『殺陣』以降、近衛に関する研究が止まっており、なんら進展がないという現状において、いずれこの『近衛十四郎の実演時代』だ議論の対象となって新しい事実が発見されたとすれば、これ以上の喜びはない。 なぜならば、私自身が本当のことを知りたいのである。 最後に、本文で触れなかったことを書き留めておく。 それは、映画界復帰後の近衛が、松竹、大映、東宝、東映といった映画製作会社ではなく、なぜ綜芸プロダクションに入ったのかということである。 プロダクションとは企画制作をする会社で、映画そのものは作らないのである。 目黒祐樹の話によれば、終戦後の近衛家では、みかんを買うこともできなかったそうだが、これほどの極貧生活を強いられることになったのは、自主制作映画の撮影が頓挫してしまったからだと思う。 調達した資金がまるまる借財として残ったはずだからである。 私はそして、自主制作映画の出演者の多くは、近衛と一座の座員だったと見ている。 だとすれば、終戦後、櫛の歯が抜けるように座員は一人減り、二人減りと少なくなっていったと思われるが、一座は正式に解散していなかった可能性が高い。 さらにいえば、独立プロ云々の思いはもうなかったろうが、唯一の食い扶持が一座の公演でもあったはずで、解散することはできなかった。 つまり、綜芸プロダクションと契約したのは近衛一座であり、演芸場でチャンバラを見せていた。 そして、近衛はその合間に映画に出演していたと見るのが正しいのではないだろうか。 近衛は松竹にいたころからコメディ資質のあることをうかがわせているが、これは、演芸場の舞台でときおりお笑いを取り入れたチャンバラをやっていたからかも知れないのである。 大都映画に、近衛と肝胆相照らす仲であり、また喧嘩友達でもあったクモイサブローという俳優がいた。 彼は、大都映画がなくなったあとは大映に残ったのだが、映画出演の機会を得ないまま召集され、復員後は剣劇一座に入り、昭和二十九年に雲井三郎と改名して映画界に復帰する。 昭和二十九年というのは近衛が松竹京都で高田浩吉の相手役として注目されはじめる時期でもある。 もし、綜芸プロ所属後も近衛が一座を存続させており、京都での仕事が忙しくなりはじめる昭和二十八年の末ごろに解散したとすれば、クモイの映画界復帰が昭和二十九年だったということには大きな意味があるはずなのである。 つまり、クモイが入った剣劇一座というのは近衛一座である可能性が高いということで、これは、綜芸プロ所属後も近衛は一座を存続させていたという証拠になるのである。 しかしこれを明らかにするには、クモイサブローの足跡を辿らなければならず、素人で、しかも勤め人でもある私ごときの手には、とても負えない作業である。 このようなこともあり、『近衛十四郎の実演時代』は取り敢えず未完とすることにした。 なお、浅香光代の登場によって人気を盛り返した女剣劇は、そのご数年を経ずしてふたたび衰微してゆき、かつてのような隆盛を極めることなく、現在に至っている。 |
|
| 参考資料 永田哲朗著『殺陣―チャンバラ映画史―』(現代教養文庫刊) 加藤厚子著『総動員体制と映画』(創元社刊) 八尋不二著『百八人の侍―時代劇と45年』(朝日新聞社) 古川隆久著『戦時下の日本映画』(吉川弘文館刊) 色川武大著『寄席放浪記』(廣済堂出版刊) 森秀男著『夢まぼろし女剣劇』(筑摩書房刊) 向井爽也著『日本の大衆演劇』(東峰出版刊) 浅香光代著『女剣劇』(学風書院刊) 大江美智子著『早替わり女剣劇一代 女の花道』(講談社刊) 大宮敏充著『デン助 浅草泣き笑い人生』(三笠書房刊) 時代劇マガジン16号(辰巳ムック) 『子から親へ ずっと書きたかった私からの手紙―松方弘樹―』(ビッグ・コミック・オリジナル) 『思い出話』(魅せる剣戟スター近衛十四郎ホームページ) |
|
|
前ページへ / 次ページへ / ホームへ |
|